こんにちは、衛生士の熊崎です。
だんだんと寒い季節が近づいてきましたね。寒暖差が激しいので体調崩しやすい時期なので気をつけてすごたいところです。インフルエンザも流行っているので手洗いうがいを徹底しましょう。
今回は疲れやすい人は要注意!歯周病と全身の関係についてのブログを書きたいと思います。

目次
はじめに|なぜ「疲れやすい」と「歯周病」が関係あるのか?
「最近、なんだか疲れが取れない…」
そんな人は、もしかすると“歯周病”が原因かもしれません。歯周病というと、歯ぐきが腫れたり血が出たりする“口の中だけの病気”と思われがちですが、実はそれだけではありません。最近の研究では、歯周病が全身の健康と深く関係していることが分かってきています。
歯周病は、細菌による慢性的な炎症です。その炎症によって、体は常に“軽い戦闘モード”のような状態になります。つまり、体が細菌と戦い続けているため、エネルギーが消耗しやすく、結果として「慢性的な疲労感」につながるのです。
また、歯周病による炎症物質(サイトカイン)は血液を通じて全身をめぐり、免疫システムにも影響を及ぼします。そのため、風邪をひきやすくなったり、体調不良が続いたりといった症状が現れることもあります。
「疲れ=過労」と思い込む前に、まずは口の中の健康を見直してみることが大切です。意外にも、あなたの“疲れやすさ”の根本原因は歯ぐきにあるかもしれません。
歯周病とは?そのメカニズムを理解しよう
歯周病は、歯と歯ぐきの間にたまった歯垢(プラーク)が原因で起こる感染症です。歯垢の中には数百種類もの細菌が存在し、その中の「歯周病菌」が歯ぐきの組織に炎症を起こします。初期の段階では「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨きのときに出血する程度です。
しかし、この段階で適切にケアをしないと、炎症がさらに深部にまで広がり、「歯周炎」へと進行します。歯を支える骨(歯槽骨)が少しずつ溶けていき、やがて歯がグラグラと動くようになります。最終的には歯を失う原因にもなるのです。
驚くべきことに、30代以上の日本人の約8割が何らかの歯周病を抱えているといわれています。つまり、ほとんどの人が“自覚のないまま進行している”というのが現実なのです。
さらに恐ろしいのは、この炎症が“口の中だけで終わらない”という点。歯周病菌や炎症物質は血液を介して全身に広がり、心臓や脳、筋肉、さらには免疫系にも悪影響を与えることがわかっています。
歯周病が引き起こす全身への影響

歯周病は“沈黙の病”とも呼ばれます。痛みがほとんどないまま進行し、気づいたときには歯ぐきだけでなく体全体にダメージを与えていることも少なくありません。
まず注目すべきは「慢性炎症」の影響です。歯周病菌が作り出す毒素や炎症性物質は血液を通して全身をめぐり、血管や臓器に微小な炎症を引き起こします。その結果、以下のような全身疾患との関連が指摘されています:
- 糖尿病:歯周病の炎症によって血糖値が上がりやすくなり、糖尿病を悪化させる。逆に、糖尿病があると歯周病も進行しやすいという“悪循環”が存在。
- 心疾患・脳梗塞:歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がる。
- 認知症:最近の研究では、歯周病菌の一種が脳内に入り、アルツハイマー型認知症の発症に関与している可能性も示唆されている。
さらに、これらの慢性炎症は体のエネルギー消費を増大させ、疲労感を強める原因にもなります。体が常に“火消し”をしている状態なので、休んでも回復しにくいのです。
疲れやすい人が歯周病を疑うべきサイン
「最近、疲れやすい」「寝てもだるさが残る」——そんなとき、歯周病を疑ってみるのも一つの手です。実は、口の中の小さなサインが全身の疲労と密接に関係しています。
代表的な症状は以下の通りです
- 歯磨きのたびに出血する
- 歯ぐきが腫れている、または下がってきた
- 口臭が気になる
- 固いものを噛むと痛みがある
- 朝起きたときに口の中がネバネバする
こうした症状が続く場合、炎症が慢性化している可能性があります。そして、体内では炎症物質が放出され続け、免疫バランスが崩れるのです。その結果、疲労感や集中力の低下、肌荒れ、肩こりなど、さまざまな不調が現れます。
また、口内環境の悪化は自律神経にも影響します。歯周病による痛みや不快感がストレスとなり、交感神経が優位な状態が続くことで、睡眠の質も低下。結果として「寝ても疲れが取れない」という悪循環に陥るのです。
歯周病を防ぐ生活習慣とは?
歯周病は「生活習慣病の一つ」とも言われます。それほど、毎日の習慣が予防と深く関係しているのです。
まず大切なのは、正しい歯磨き。歯ブラシは毛先が細く柔らかいものを選び、歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、優しく小刻みに動かすのがポイントです。また、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは落ちにくいので、デンタルフロスや歯間ブラシも併用しましょう。
次に、食生活の改善です。糖分の多い食べ物や加工食品は、歯周病菌のエサになります。一方で、ビタミンCやカルシウム、たんぱく質を多く含む食品(野菜・魚・大豆製品など)は歯ぐきの健康を保ちます。
さらに、ストレスと睡眠の質も重要です。ストレスが続くと免疫力が下がり、歯周病菌が活発になります。夜更かしや不規則な生活を避け、しっかりと休息を取ることが予防の第一歩です。
歯周病と生活習慣病の「悪循環」
歯周病は、ただの口のトラブルにとどまらず、糖尿病や心疾患など、さまざまな生活習慣病と深く結びついています。特に糖尿病との関係は「双方向性」と呼ばれ、お互いに悪影響を及ぼすことが知られています。
歯周病の炎症が体内のインスリン抵抗性を高めると、血糖値が上がりやすくなります。反対に、糖尿病で血糖コントロールがうまくいかないと、免疫力が低下し、歯周病菌が繁殖しやすい環境が整ってしまいます。つまり、歯周病と糖尿病はお互いを悪化させる“負のスパイラル”を作り出すのです。
また、歯周病菌が血管内に侵入すると、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳梗塞のリスクを高めます。細菌による炎症反応が血管の壁を傷つけ、血栓を作りやすくするのです。このように、歯周病はまさに「体の中で静かに進む炎症の火種」と言えるでしょう。
さらに、女性の場合は妊娠中のホルモンバランスの変化により、歯周病が悪化しやすくなります。妊娠中の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることも知られており、母体だけでなく胎児にも影響を及ぼします。
全身の健康を守るためには、歯や歯ぐきのケアを「美容やマナー」ではなく「健康維持の基本」として考える必要があります。
歯周病が引き起こす“隠れ疲労”のメカニズム
「ちゃんと寝ているのに疲れが取れない」——そんな“隠れ疲労”の原因のひとつに、歯周病による慢性炎症があります。
私たちの体は、炎症が起こると免疫細胞が活性化し、細菌を排除するために多くのエネルギーを消費します。このとき、体内では活性酸素が大量に発生し、細胞が酸化ストレスを受けるのです。酸化ストレスが蓄積すると、筋肉や神経の働きが低下し、慢性的な倦怠感や集中力の低下につながります。
さらに、歯周病による炎症は自律神経にも影響します。交感神経が過剰に働き、常に“緊張モード”が続くことで、リラックスを司る副交感神経の働きが抑えられます。その結果、睡眠の質が低下し、夜休んでも疲れが抜けないという状態に陥るのです。
つまり、歯周病は「体の疲れスイッチを押しっぱなしにする病気」と言っても過言ではありません。歯ぐきの炎症を放置することは、知らぬ間に体全体を疲れさせる行為なのです。
歯医者に行くべきタイミングとは?
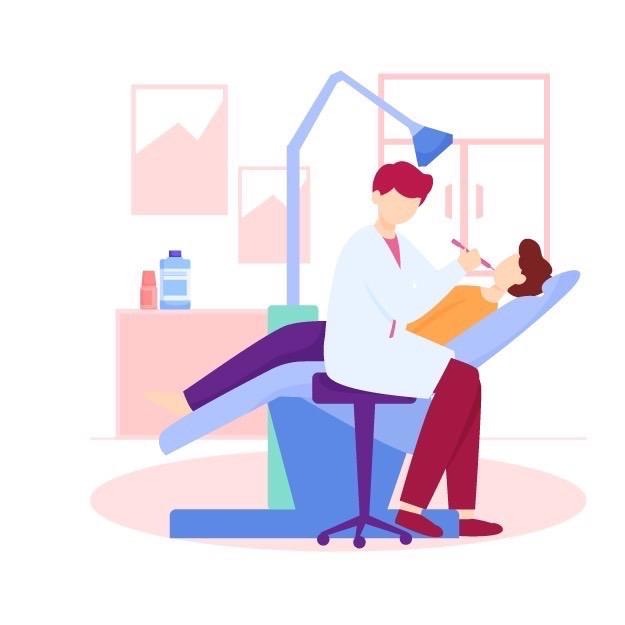
「痛みがないから大丈夫」と思っていませんか?
実は、歯周病は“痛みが出にくい病気”の代表格です。気づいたときには進行しているケースが多いため、定期的な歯科検診が何よりの予防になります。
歯ぐきの色が赤く腫れている、歯が少し動く、口臭が気になる、そんな些細なサインでも早めに受診しましょう。歯科医院では、歯石除去(スケーリング)や深部のクリーニング(ルートプレーニング)を行い、炎症の原因を取り除くことができます。
また、最近では歯周病の進行度を調べる「歯周ポケット検査」や「細菌検査」も行われています。これにより、自分の口内環境やリスクを可視化し、効果的な治療計画を立てることができます。
重要なのは、“痛みが出てから行く”のではなく、“悪くなる前にチェックする”という意識。歯周病は予防と早期発見がすべてです。
歯周病対策に効果的な栄養素とは?
食生活は、歯ぐきの健康に直結します。以下の栄養素を意識的に取り入れることで、歯周病予防や改善に役立ちます。
栄養素 主な働き 含まれる食品例
- ビタミンC 歯ぐきのコラーゲン生成を促進し、炎症を抑える キウイ、ブロッコリー、パプリカ、みかん
- カルシウム 歯と骨を強化し、歯を支える力を高める 牛乳、ヨーグルト、小魚、チーズ
- オメガ3脂肪酸 炎症を抑制し、血流を改善 サバ、イワシ、アマニ油
- ポリフェノール 抗酸化作用で細胞の老化を防ぐ 緑茶、ブルーベリー、赤ワイン
- たんぱく質 歯周組織の修復を助ける 鶏むね肉、豆腐、卵
特に、ビタミンCは歯ぐきの血流を改善し、出血や腫れを抑える効果があるため、毎日の食事でしっかり摂取しましょう。
正しい歯磨き法で歯ぐきを守る
「毎日磨いているのに歯周病が進行している」——それは、磨き方が間違っている可能性があります。
歯周病予防のカギは、“プラークを残さない”磨き方です。ポイントは以下の3つ:
- 歯ブラシの角度は45度
歯と歯ぐきの境目に毛先を当て、小刻みに動かすことで汚れをしっかり落とせます。 - 力を入れすぎない
強く磨くと歯ぐきを傷つけ、逆に炎症を悪化させてしまうことも。 - 1日2~3回、3分以上
特に寝る前のブラッシングは最も重要。寝ている間に細菌が繁殖しやすいためです。
さらに、歯ブラシだけでは落とせない汚れにはデンタルフロスや歯間ブラシを使用しましょう。これにより、歯と歯の間に潜む歯垢を除去でき、炎症の発生を大幅に防ぐことができます。
まとめ|“口の健康”が“全身の元気”を支える
疲れやすさの原因は、必ずしも体の外にあるとは限りません。実は、毎日の食事や会話を支える「口の中」が、全身の健康のバロメーターになっているのです。
歯周病を放置すると、知らぬ間に体内で炎症が続き、免疫力やエネルギー代謝に影響を及ぼします。その結果、「疲れやすい」「だるい」「集中できない」といった症状が現れることも少なくありません。
だからこそ、定期的な歯科検診、正しいセルフケア、そして栄養バランスのとれた食生活が大切です。
“口の中の健康”を整えることは、“体全体の健康”を守る最も身近で確実な方法なのです。
よくある質問(FAQ)
Q1:歯周病は治りますか?
A1:初期段階であれば、正しいケアと治療で改善が可能です。進行している場合でも、炎症を抑え、進行を止めることはできます。
Q2:歯磨きで血が出るのは歯周病ですか?
A2:はい、歯ぐきの炎症が進んでいるサインかもしれません。早めに歯科を受診しましょう。
Q3:歯周病はうつりますか?
A3:歯周病菌は唾液を介して感染するため、家族やパートナー間でうつる可能性があります。
Q4:どんな人が歯周病になりやすいですか?
A4:喫煙者、糖尿病患者、ストレスが多い人、睡眠不足の人は特にリスクが高いとされています。
Q5:疲れやすさが続くとき、どの診療科に行けばいい?
A5:まずは歯科で口腔内のチェックを受けましょう。原因が歯周病以外の場合は、内科や睡眠外来を紹介してもらえることもあります。
放置しておくと歯を失う大きな原因になるので定期的な歯科検診へ行きましょう。ご自身の歯磨きもレベルアップできるようお手伝いします!


